 |
|
 |
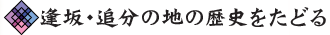 |
|
京都市と大津市を隔てる逢坂山・追分は、かつて、京の都の玄関口として、東海道をゆく多くの旅人で賑わいました。
この付近には、清らかな水が勢いよくあふれ出す井戸があり、その様から『走井(はしりい)』と呼ばれ、旅人ののどを潤しました。
江戸時代になると周囲には茶店が建ち並び、旅人のオアシスになりました。そこで売り出された『走り井』の甘露でついた餅菓子は、その名を冠して『走り井餅』と呼ばれました。
以来、『走り井餅』は旅人をいやし、逢坂の地で長く親しまれる銘菓となったのです。 |
 |
 |
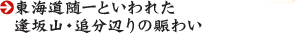 |
| |
わが国最大の交通の要、逢坂関 |
| |
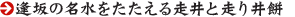 |
| |
今も湧き続ける走井 |
| |
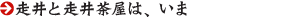 |
| |
旅人のオアシス・走井茶屋 |
| |
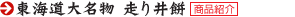 |
| |
第二十三回全国菓子大博覧会 名誉総裁賞受賞 |
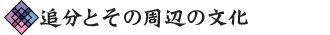 |
| 追分の地は、西本願寺の門前町が移転し、京の技術者の集団となり、日本そろばん、走り井餅、大津絵、みすや針などの発祥の地となりました。 |
 |
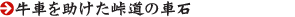 |
| |
京都-大津間に敷設され、運搬を助けました |
| |
 |
| |
当時の風俗を今に伝える民衆芸術 |
| |
 |
| |
追分は、日本のそろばん発祥地 |
| |
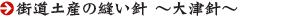 |
| |
博覧会にも出品された街道名物 |
|
 |
|
|

